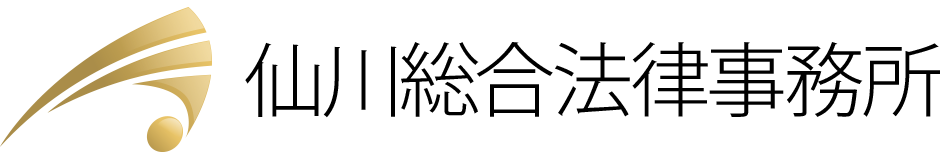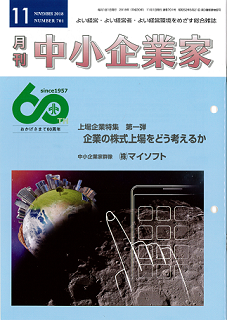お知らせ
【コラム】法律お役立ちコラム《債務整理_vol8》
破産事件について~破産管財人が就く場合と就かない場合
1 はじめに
破産事件には、破産管財人が就く場合(「管財事件」)と、破産管財人が就かないで「同時廃止」として手続きが終了する場合があります。
破産管財人が就く場合には、引継予納金と言う費用を納める必要があり、その金額は東京地方裁判所の場合は最低20万円とされています。
同時廃止の場合は、このお金は必要ありません。
従って、破産管財人が就く場合と就かない場合のどちらになるかは、申立てをする方にとって大きな負担の違いがあります。
2 同時廃止とは/破産管財人とは
同時廃止とは、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると裁判所が認めたとき」に、破産手続開始決定と同時に破産手続きを廃止するものです(破産法216条1項)。
破産管財人とは、破産手続きにおいて、破産財団に属する財産の管理・処分等を行う者を言います(破産法2条12項)。
破産管財人は、破産手続きの開始決定と同時に、裁判所が選任します。
破産管財人には法的知識が不可欠のため、弁護士から選任されることになります。
3 同時廃止と管財事件の区別の基準
では、どのような場合に同時廃止となり、どのような場合に管財事件となるのでしょうか。
東京地方裁判所では、以下のような場合には、原則として管財事件として扱うものとされています。
・20万円を超える現金がある場合
・20万円を超える換価対象財産がある場合
例えば、20万円以上の預貯金や積立金、保険の解約払戻金、不動産などがある場合です。
・資産調査が必要な場合
・法人及び法人の代表者の場合
・個人事業者の場合
・免責調査を経ることが相当な場合
例えば浪費などの免責不許可事由がある場合は、管財人による調査が必要となります。
以上の場合には、原則として破産管財人が就任することになります。
ただし、ご相談段階で上記のいずれかにあたる場合であっても、事情によっては管財事件とならずに同時廃止として破産手続きを進められることもあります。
当事務所では、管財事件となるか同時廃止になるか、具体的事情に応じて事前に見通しをお伝えすることが可能ですので、まずはご相談ください。
年末年始休業のお知らせ
当事務所は2018年12月29日(土)から2019年1月3日(木)まで 休業とさせていただきます。
新年は1月4日(金)午前9時30分より業務を開始いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
カネボウ美白化粧品白斑被害事件(東京訴訟)終了の報告
カネボウ美白化粧品白斑被害事件(東京訴訟)終了の報告
1
平成30年12月17日、当事務所の弁護士伊藤真樹子が弁護団として活動してきたカネボウ美白化粧品白斑被害事件(東京訴訟)が終了しましたので、ご報告致します。
この事件は、カネボウが製造販売した美白化粧品で白斑様の症状が発生するという被害を被った原告らを救済するために提訴した訴訟です。
2
当弁護団は、平成25年10月に結成され、カネボウを被告として、東京地方裁判所に対し、平成27年4月に第1次訴訟(原告27名)、同年7月に第2次訴訟(原告13名)を提起して訴訟活動を行ってまいりましたが、本日(2018年12月17日)、訴訟手続を調停手続に移行させた上、原告39名全員(途中1名訴えを取り下げた)とカネボウの間で調停が成立し、東京訴訟が終了し解決したことを報告いたします。
3
成立した調停の具体的な内容は非開示特約が付されているために公表できませんが,その骨子は,次のとおりです。
①原告ら全員とカネボウの間で調停が成立したこと
②カネボウは、「本件化粧品を使用された申立人に白斑様症状が生じたことについて深く反省し、肌に直接触れる製品をお届けするメーカーとしての責任を重く受け止め、心よりお詫びするとともに、再発防止に努める。」ということを表明しました。
4
調停の具体的内容や交渉経緯を公表できないことは残念ですが、上記の通りカネボウから明確な謝罪条項を得たことは大きな意味があるものと考えています。
今後、カネボウのみならず、他の全ての化粧品メーカーが、「肌に直接触れる製品をお届けするメーカーとしての責任」に真摯に向き合い、単なる経済的利益のみを追求した安直な新商品の開発に走ることなく、消費者にとって真に安全な商品を提供していくことを切に願います。
記者会見の様子はこちらをご覧ください
《NHK NEWS WEB》 (https://www3.nhk.or.jp/lnews/shutoken/20181217/1000022731.html)
《TBS NEWS》 (https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3551836.html)
【お知らせ】弁護士ドットコムニュース記事が公開されました
伊藤真樹子弁護士が解説した弁護士ドットコムニュース記事が公開されました。
是非ご覧ください。
◆将来の不貞行為に関する慰謝料について(弁護士ドットコムニュース)