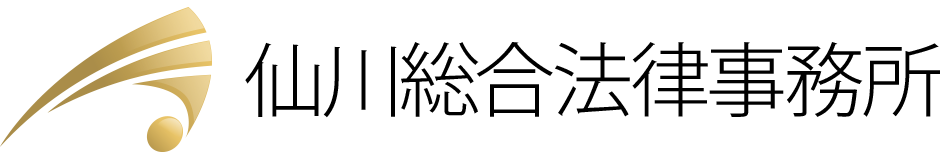お知らせ
【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol12》
養育費や婚姻費用の履行を確保する手段~履行勧告、強制執行
1
養育費や婚姻費用について、調停や審判でせっかく取り決めをしても、その後実際の支払いがストップしてしまうことがあります。
そのような場合に、履行を確保するための手段としては、家庭裁判所から履行勧告をしてもらう方法と、強制執行をする方法があります。
2 履行勧告について
① 履行勧告とは
履行勧告とは、審判や調停によって定められた義務の履行を怠っている義務者に対し、家庭裁判所が権利者の申出により、義務の履行状況を調査したうえで、その履行を勧告する制度です。
② 履行勧告の効力
履行勧告は、あくまで裁判所からの勧告であり、支払いを強制する効力はありません。
ただ、裁判所から直接義務者に連絡が入り、履行するよう勧告されることで、単に義務者から請求を受けるよりも心理的なプレッシャーは大きいと言えるでしょう。
実際、履行勧告があったことでその後支払いがなされるようになったケースは少なくありません。
3 強制執行について
① 強制執行とは
裁判所を通じて、強制的に取り立てる手段です。
債務者が債務の支払いを任意にしない場合に、民事執行法に基づいて裁判所に申立てをすることによって手続きが行われます。
② 強制執行ができる財産
強制執行が出来るのは、債務者名義の財産です。
給与や預貯金、不動産、自動車など幅広い財産が対象となります。
給与の差押えについては、通常の債権の場合には、給与の4分の1までしか差押えが出来ませんが、養育費や婚姻費用の場合には特別に2分の1まで差し押さえることが認められています。
③ 強制執行をするために必要な書類
強制執行をするためには、「債務名義」と呼ばれる特別な書面(強制執行の根拠となる書面)が必要です。
調停調書や、強制執行認諾文言付きの公正証書などがこれにあたります。
単なる口約束や、当事者間で誓約書を作成していただけでは、強制執行の手続きを取ることは出来ません。
そのため、養育費や婚姻費用について取り決めをする際には、支払いが滞った場合の強制執行まで視野に入れて書面を作成しておくことが重要です。
【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol11》
財産分与
婚姻期間中に形成された財産は、特別な事情がない限り夫婦の共有財産となります。
仮に妻が専業主婦であったとしても、妻の協力があってこそ夫が収入を得ることが出来たわけですから、夫婦で得た財産は基本的には全て共有財産となります。
ご自宅不動産の名義が夫の単独所有となっていることもよくありますが、法的には名義に関わらず実態を判断しますので、夫婦の共有財産として扱われます。
1 分与の対象となる財産
一般的に、妻と夫が所有している財産として、婚姻後に形成されたものだけでなく、婚姻前からの財産が含まれていることも多くあります。
離婚にあたっては、そのような財産全体の内、どの財産が分与の対象となるのかを判断しなければなりません。
その判断は、以下の分類に沿って検討されます。
①特有財産
名実共に夫婦それぞれの所有である財産を言います。
婚姻前から各自が所有していたものや、婚姻中に一方が相続や贈与により取得したものなどがこれにあたります。
特有財産については、財産分与の対象とはなりません。
②共有財産
名実共に夫婦の共有に属するもの。
夫婦が合意で共有とし、共同名義で取得した財産、婚姻中に取得した共同生活に必要な家財、家具等が含まれます。
共有財産は、当然に財産分与の対象となります。
③実質的共有財産
名義は一方に属するが実質的には夫婦の共有に属するもの。
上記で説明したような、婚姻期間中に購入したマイホームが夫単独の名義になっている場合が典型例です。
その他、自家用車、共同生活の基金とされる預金、株券等で夫婦の一方の名義になっているものが含まれます。
実質的共有財産は、清算対象の財産ではないという特別な事情がない限り、財産分与の対象とされます。
2 財産分与の割合
基本的には、財産形成に対する夫婦それぞれの貢献度によって決めることになります。
ただ、実際の裁判や調停では、夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦が協力して形成したのであり、その貢献度は平等であるとされています。
従って、分与の割合は、2分の1が原則となります。
3 財産分与の判断の基準時
既に別居しており、別居後に一定の財産が形成されているような場合には、どの時点での財産を分与対象にするのか、争いになることがあります。
これついては、裁判時(口頭弁論終結時ないし審判時)とする説、別居時とする説、離婚時とする説の3つがあり、判例や学説は統一されていないのが実情です。
ただ、実務においては、一応夫婦の協力関係の終了する別居時を基本とし、公平の見地から、事情によりその後の財産の変動も考慮して妥当な解決を図ることが一般的です。
財産分与については、財産の調査や分与方法など、専門的な知識が必要になるケースが多く、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
【お知らせ】調布・狛江 市民法務無料相談会(11・12・1月開催)が開催されます

調布行政書士市民法務会主催の「調布・狛江 市民法務無料相談会」に相談員として参加します。
※ 伊藤弁護士が参加できない日程もございますので、詳しくは事務所(仙川総合法律事務所)にお問い合わせください。
◆日程・場所◆ ※最終受付は終了時間30分前です
2017年
11月 9日(木)10:00~13:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)
11月16日(木)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
11月25日(土) 9:00~12:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
11月28日(火)13:00~16:00 狛江市商工会館 2階会議室(狛江駅 徒歩3分)
12月 7日(木)13:00~16:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)
12月16日(土)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
12月26日(火)13:00~16:00 狛江市防災センター 4階403会議室(狛江市役所隣り)
2018年
1月20日(土)13:00~16:00 市民プラザあくろす 2階 会議室1(京王線国領駅北口 コクティー)
1月31日(水)13:00~16:00 調布市文化会館たづくり 8階 801会議室
※ 予約不要・相談無料です。
※ 相続、遺言、離婚 など、身近な問題についてご相談を承ります。
詳細はコチラ【調布 市民法務会】でご確認下さい。
【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol10》
婚約破棄と損害賠償請求
1
結婚をしていなくても、婚約が成立した後に身勝手な理由で一方的に婚約を破棄する場合には、法的に損害賠償義務が発生する場合があります。
ただ、そのような法的な責任が発生するのは、単なる当事者の一方的認識ではなく法的に婚約が成立したと認められること、婚約破棄について正当な理由がないことが必要です。
以下、それぞれについてご説明します。
2 婚約の成立
婚約は、「婚姻の予約」という契約であり、その成立のためには、必ずしも結納や婚約指輪の交換などの行為は必要ありません。
ただ、単に交際中に「将来結婚しよう。」と話をしていただけでは法的な婚約の成立とはなりません。
具体的には、当事者間に婚約の合意があったか否かを客観的事情なども考慮して判断することになります。
例えば、親族等第三者への紹介、結婚式場の予約の有無などが判断要素となります。
3 婚約破棄の正当な理由
どちらかが婚約の破棄をしても、それが正当な理由に基づく場合には損害賠償義務は発生しません。
例えば、婚約成立後の不貞行為、暴力や暴言、経済状態の急変など、今後婚姻をすることが社会通念上困難な状態となることが認められるような場合には、正当な理由に基づく婚約破棄とされます。
4 請求できる損害と慰謝料の相場
正当な理由なく婚約を破棄された場合、当然のことながら相当な精神的ショックを被ることになりますので、これを慰謝させるための慰謝料を請求できます。
慰謝料の金額については、交際期間や婚約期間、婚約破棄の理由などを総合的に考慮して判断されることになりますが、一般的な相場は50万円から300万円程度です。
また、慰謝料以外にも、婚約破棄によって生じた損害についても、賠償請求できる可能性があります。
例えば、新居準備費用、結婚式のキャンセル料、引き出物費用、新婚旅行の費用などは認められる可能性が高いでしょう。
5
当事務所では、婚約破棄をめぐるトラブルについても多数の解決実績を有しております。まずはお気軽にご相談ください。
【コラム】法律お役立ちコラム《離婚_vol9》
内縁関係の解消と慰謝料、財産分与
1 内縁関係とは
内縁関係とは、結婚の届出がないだけで、実質的には夫婦である状態を言います。
内縁関係については、出来る限り婚姻に準じて考えるべきとされており、内縁関係が解消される場合にも、基本的には離婚に準じた法的効果を認めるべきというのが一般的な考え方です。
ただし、単に婚約中だとか、恋人として同棲中だったり、愛人関係というだけでは内縁関係とは認めず、あくまで実質的には夫婦と言える状態であることが必要です。
内縁関係が成立していると言えるかどうかは、次のような観点から判断されます。
①当事者間に婚姻の意思があること
婚姻届を提出していなくても、当事者同士は夫婦として認識していることが必要です。
単なる恋人同士や同居人などの認識では内縁関係とは認められません。
②夫婦の共同生活の実態があること
世間一般的に見て、「夫婦」と呼べるような生活実態がなければなりません。
例えば、同居していること、生活費を一緒にしていること、子どもを二人で協力して育てていることなどが判断材料となります。
2 内縁の解消と慰謝料、財産分与
内縁の解消は、離婚と異なり、共同生活が事実上行われなくなると解消されます。
上記の通り、内縁関係にもできる限り婚姻に準じた法的効果を認めるべきというのが一般的な考え方ですので、内縁関係の解消に際しても、離婚と同様に慰謝料や財産分与の請求が可能です。
請求の基準や内容も、出来る限り離婚に準じて考えるのが原則です。
請求の方法としては、当事者間の話合いで定めるのが原則ですが、話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
調停でも話合いがまとまらなければ、裁判を起こすことが出来ます。
3 内縁関係にある夫婦の子どもについて
内縁関係にある当事者間に生まれた子どもは非嫡出子であり、母親の戸籍に入り、親権も母親の単独親権となります。
父親との関係は、婚姻届がない状態で認知もしていないと、法的には何らの関係も持ちません。
内縁関係の解消後に養育費を請求するためには、前提として、必ず認知がなされていなければなりません。
認知がなされている場合には、養育費の請求についても、離婚の場合と同様に考えられます。
男性が親権を獲得したい場合には、認知しただけでは足りず、父母の協議又は家庭裁判所の決定が必要です。
また、子どもが父の戸籍に入るためには、家庭裁判所に申し立てて子の氏の変更許可を得る必要があります。
当事務所では、内縁関係の解消に伴う法的問題についても多数の解決実績があります。どうぞお気軽にご相談ください。